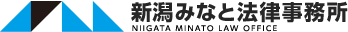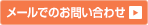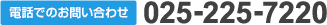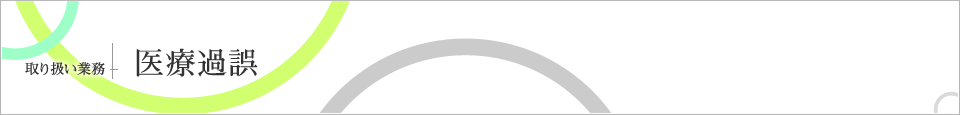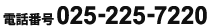医療判例紹介-術後管理をする医師の注意義務
【最高裁平成18年4月18日判決】
(事案)
患者は、冠状動脈に狭窄が認められたことから、平成3年2月22日、冠状動脈バイパス手術を受けた。術後は良好な経過を辿っていたが、翌23日夕刻、腹痛を訴え始め、24日午前0時ころから頻繁に腹痛を訴えるようになり、「何で。何で。」「助けてどうしようもない。」「きつい、きつい」等と訴えていた。担当医は、精神的不安によるところが大きいと考え、抗不安薬を注射したり、鎮痛剤を投与するなどして対応していた。同日未明には高度のアシドーシスとなり、担当医は腸管壊死を考えたが、よくわからず、様子を見ていた。同日早朝にはマスクを外す動作を繰り返し、つじつまの合わないことを話し、腹痛を訴えていた。担当医は、同日午前8時までの間に、アシドーシス、肝機能障害、腎機能障害が認められたので、腸閉塞と判断し、腸のぜん動を促す薬を投与したが、効果がなかった。その後患者は不穏状態となり、投薬にもかかわらず意識レベルが少しずつ落ちてきて、全身状態が悪化していった。担当医は、同僚医師と相談の上、開腹手術を行うこととし、同日午後3時または4時ころ、冠状動脈バイパス手術の執刀医であった教授と連絡を取り、 同日午後6時過ぎころ、教授と担当医が家族に開腹手術の説明をした。家族は手術承諾書への署名を一度拒んだが、最終的には署名し、同日午後7時20分より開腹手術が行われた。手術時の所見では、腹腔内に多量の腹水があり、大腸には広範な壊死が認められ、小腸にも壊死が散在していたため、小腸、大腸部分切除、胆嚢摘出、人工肛門増設の処置が行われたが、その後患者の意識は回復することなく、急性腎不全、急性心不全を来たし、25日午後0時55分に死亡した。
(判旨)
(1)平成3年当時の腸管壊死に関する医学的知見では、腹痛が常時存在し、増強するとともに、高度のアシドーシスが進行し、腸閉塞の症状が顕著になり、腸管のぜん動運動を促進する薬を投与するなどしても改善がなければ、腸管壊死の発生が高い確率で考えられていたというのであり、本件患者もこのような状況にあったこと、(2)当時の医学的知見では、腸管壊死であるときは、直ちに開腹手術を実施し、壊死部分を切除しなければ救命の余地はないとされていたこと、(3)患者は、開腹手術の実施によってかえって生命の危険が高まるために同手術の実施を避けることが相当といえるような状況にはなかったこと、(4)患者の症状は次第に悪化し、経過観察によって改善を見込める状態にはなかったことなどの事情からすれば、担当医には、患者に腸管壊死が発生している可能性が高いと診断し、直ちに開腹手術を実施し、腸管に壊死部分があればこれを切除すべき注意義務を怠った過失がある。
医療過誤に関するご相談は、新潟みなと法律事務所にお任せください。
⇒お問い合わせ・ご相談の予約はこちら